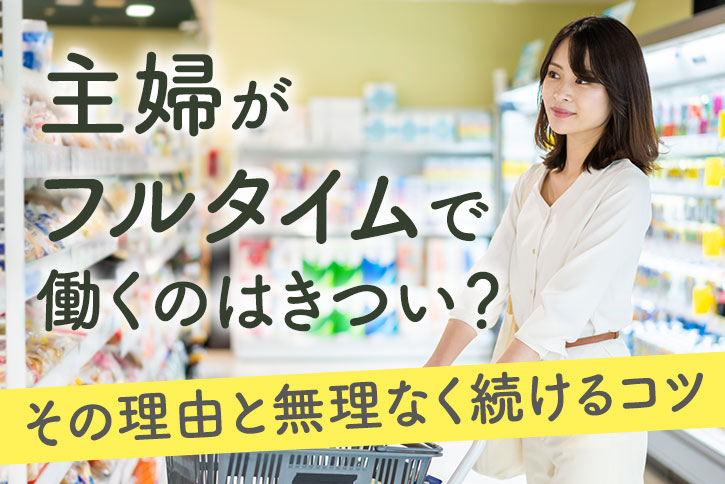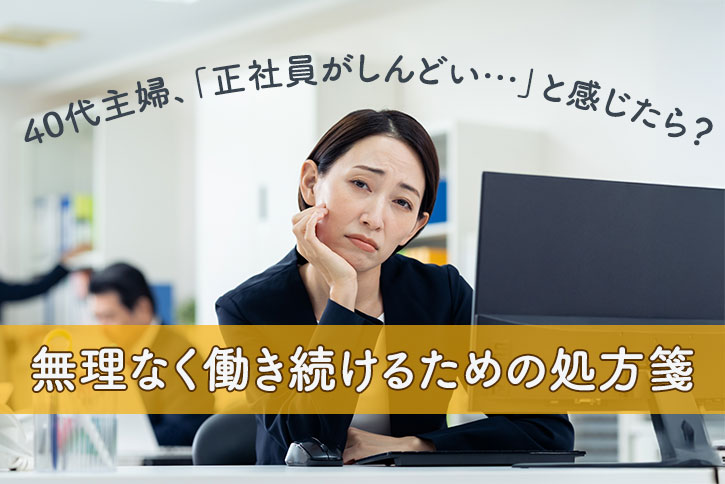就業中の豆知識
派遣社員でも確定申告が必要になる4つのケース!やり方も解説
公開日:2024.05.13
更新日:2025.11.25

税金に関する手続きのひとつである「確定申告」ですが、派遣社員も行うべきなのか、気になる方もいることでしょう。派遣社員は給与所得者のため、基本的には必要ありませんが、なかには必要になるケースもあります。
本記事では2025年(令和7年)時点の最新制度に対応し、確定申告の基本とやり方、派遣社員で確定申告が必要なケースや、よくある疑問についてわかりやすく解説します。
目次
- 【はじめに】派遣社員の確定申告ポイントまとめ
- 派遣社員は原則として確定申告不要
- 年末調整を受けていない場合
- 派遣会社が年末調整をしてくれない場合
- 派遣の収入以外に副収入があり、その所得が20万円を超える場合
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税など、年末調整では対処できない控除を受ける場合
- 年間の給与収入が2,000万円超の高所得者の方
- 110万円を超える贈与を受けた場合
- 給与に通勤交通費が含まれている場合
- 確定申告とは?年末調整と何が違う?
- 派遣社員で確定申告が必要なケース
- 確定申告の基本
- 派遣社員の確定申告のやり方
- 確定申告をしなかった場合のリスク
- 派遣社員の確定申告に関するよくある疑問
- 派遣社員で確定申告が必要なケースを把握しておこう
【はじめに】派遣社員の確定申告ポイントまとめ
派遣社員の方が確定申告をする必要があるかどうか、よく質問にあがるポイントを以下にまとめています。
・派遣社員は原則として確定申告不要
派遣会社による年末調整で所得税が精算されているため、通常は自分で確定申告する必要はありません。
・年末調整を受けていない場合
払い過ぎた税金を取り戻すために自分で確定申告を行う必要があります。(例:12月時点で派遣契約が終了していた場合など)
・派遣会社が年末調整をしてくれない場合
自分で確定申告を行う必要があります。(例:年末調整の対象外となった場合など)
・派遣の収入以外に副収入があり、その所得が20万円を超える場合
確定申告が必要です。副収入が20万円以下でも、医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合は副収入分も含めて申告できます(詳しくは副業の確定申告の記事も参照してください)。
・医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税など、年末調整では対処できない控除を受ける場合
確定申告が必要です。たとえば医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額を超えると適用できますし、住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要になります(2年目以降は年末調整で手続き可能)。
・年間の給与収入が2,000万円超の高所得者の方
勤務先で年末調整が行われないため、自分で確定申告をしなければなりません。110万円を超える贈与を受けた場合や一時所得(保険金や懸賞金など)を得た場合も、確定申告(贈与税の申告を含む)が必要です。
・110万円を超える贈与を受けた場合
110万円を超える贈与を受けた場合や一時所得(保険金や懸賞金など)を得た場合も、確定申告(贈与税の申告を含む)が必要です。
・給与に通勤交通費が含まれている場合
給与に通勤交通費が含まれており、その分まで源泉徴収されている場合は、確定申告を行えば払い過ぎた税金の還付を受けられる可能性があります。
確定申告とは?年末調整と何が違う?

確定申告と混合されがちなものに、年末調整があります。確定申告とは、所得税や住民税を納税するために個人が申告書類を提出するものですが、年末調整は所得税の過不足を調整するために、基本的に会社が行ってくれるものです。
まずは確定申告と年末調整の違いについて解説します。
| 確定申告とは
確定申告とは、日本国内で所得税や住民税を納めるための手続きです。毎年1月1日から12月31日までに得た所得と所得税を計算し、書類を作成したうえで税務署に申告します。所得と比べて、源泉徴収税額や予定納税額が多い場合は、還付金が受け取れます。
派遣社員を含む給与所得者は、源泉徴収された所得税や住民税をすでに給与から天引きされています。そのため、2ヵ所以上で給与を受け取っているなどの特別なケースを除いて確定申告の必要はありません。
| 年末調整とは
年末調整とは、所得税の過不足を精算する手続きであり、会社が行ってくれる「確定申告」と考えるとわかりやすいでしょう。給与所得者の場合、毎月の給与から「源泉徴収」の名目で、所得税が天引きされています。
しかし、この数字は概算であり、実際の所得税との誤差が発生する可能性があります。年末調整は誤差を修正し、還付または追加徴収する役目を担っています。
基本的に年末調整は、派遣会社が行ってくれます。ただ、まれに年末調整をしてくれない派遣会社もあるため、注意が必要です。注意点については後述します。
派遣社員で確定申告が必要なケース

派遣社員の場合、基本的に派遣会社が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、下記のいずれかに当てはまる場合は確定申告が必要です。
- ・年末調整時に派遣会社に雇用されていない
- ・派遣会社が年末調整をしてくれない
- ・派遣以外で20万円超の副収入がある
- ・医療費控除や住宅ローン控除などを利用したい
内容について詳しく解説します。
| 年末調整時に派遣会社に雇用されていない場合
12月の年末調整を行うタイミングで派遣会社との雇用関係がない場合は、年末調整をしてもらえません。例えば、夏に派遣契約が終了し、12月の時点で次の派遣先が決まっていない状態などが挙げられます。
この場合は、自分で確定申告をすることで、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
| 派遣会社が年末調整をしてくれない場合
派遣元企業との雇用契約のタイミングによっては、年末調整をしてもらえないケースもあります。例えば、12月1日から雇用契約が始まったとしても、派遣会社のルールが「11月中に雇用契約をしていること」であれば、年末調整の対象外です。
そのほか、年末調整に必要な書類が締切までに揃えられずに提出できなかった場合や、年末調整後に扶養家族の人数に変化があった場合なども、個人で確定申告を行う必要があります。
| 派遣以外で20万円超の副収入がある場合
年末調整をしてくれる派遣元での収入以外に、副業やアルバイトをしている方は注意が必要です。アルバイト・パートなど給与を受け取っている場合は給与収入20万円以上、サイドビジネスやクラウドソーシングなどの場合は所得20万円以上で確定申告が必要です。
副収入が20万円以下であっても、医療費控除や住宅ローン控除などを利用したい場合は、確定申告が必要です。次で詳しく説明します。
| 医療費控除や住宅ローン控除などを利用する場合
年末調整では大部分の控除手続きをしてもらえるものの、医療費控除や住宅ローン控除など一部例外があります。医療費控除は、原則として1年間に10万円以上医療費を支払った場合、領収書をもとに計上できます。
住宅ローン控除の場合、2年目以降は年末調整が可能ですが、1年目は確定申告が必要です。ほかにも自宅を売却したケースなど、いくつかのケースで確定申告が必要となります。


確定申告の基本

確定申告を行うにあたっては、事前の準備が必要です。ここではスケジュールと申告先、不明点の相談窓口、万が一確定申告期限に遅れてしまった場合の措置方法について紹介します。
| スケジュール
確定申告の期間は、原則として申告対象の年(1月1日〜12月31日)の翌年2月16日〜3月15日です。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、期限の延長が行われました。また、令和6年能登半島地震の被災者にも、申告期限の延長措置が取られています。
このように、世の中の情勢により確定申告期限が変更される場合があるため、確定申告を行う前に期限を確認することをおすすめします。
| 申告先と相談窓口
確定申告の手続きを行うのは、住民票がある自治体の税務署です。国税庁のホームページには「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」が設けられているため参考にしてみましょう。
相談窓口について、下記表にまとめました。

※参考 国税庁「税についての相談窓口」
| 遅れてしまったときの措置
確定申告は、提出期限が過ぎても税務署に受け付けてもらえます。この場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるケースがあります。
ただし、確定申告の期間内の納税が難しく遅れそうな場合も、理由によっては制度を活用できます。まず、災害により財産を失った場合など、納付により生活が困難になると考えられる場合は「猶予制度」が使えるケースがあります。
また、所属税の納付が遅れそうな場合、3月15日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付することで、残りの納付期限を5月31日に延長できます。ただし、利子が発生するため、納税額が高くなる点に注意が必要です。
派遣社員の確定申告のやり方

派遣社員は、副業収入がある、年末調整されていない、医療費控除や寄附金控除を受けたいなどの場合には確定申告が必要です。確定申告にあたり準備すべき主な書類とその入手方法は以下の通りです。
必要書類を準備する
- ・源泉徴収票(派遣会社など各勤務先から取得)
- ・本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証など)
- ・生命保険・地震保険の控除証明書(該当者のみ、保険会社から取得)
- ・社会保険料控除証明書(国民年金保険料等、該当者のみ、日本年金機構や自治体から取得)
- ・医療費控除の明細書(該当者のみ、自身で作成)
- ・寄附金受領証明書(該当者のみ、寄附先から取得)
- ・その他の収入に関する書類(副業収入の源泉徴収票・収支内訳書等)
源泉徴収票
派遣会社は毎年1月末までに「給与所得の源泉徴収票」を交付します。年間の給与支払額と源泉徴収税額が記載された重要書類で、確定申告に必須です。
本人確認書類
確定申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。写真付きのマイナンバーカード1枚で番号確認および身元確認が可能です。それがない場合は通知カード(またはマイナンバー入り住民票)と運転免許証などの身分証の組み合わせで確認します。
生命保険・地震保険の控除証明書
生命保険や地震保険に加入している人は、保険会社から毎年郵送される控除証明書を確定申告時に提出して支払額を証明します。
社会保険料控除証明書
自分で国民年金保険料を納付している人は、日本年金機構発行の控除証明書を添付します。また、国民健康保険料なども市区町村発行の納付証明書や領収書で証明します。
医療費控除の明細書
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を作成して申告書に添付します。医療費の領収書は提出不要ですが、5年間保管しましょう。
寄附金受領証明書
寄附金控除を受けるには、寄附先から交付される寄附金受領証明書を申告書に添付する必要があります。証明書は寄附後に郵送されるので、必ず保管しましょう。
その他の収入に関する書類
副業収入がある場合は、その種類に応じて副業先の源泉徴収票や収支内訳書など収入を証明する書類を用意します。
| 確定申告書を作成する
書類の準備を終えたら、確定申告書の作成へと進みます。主な作成方法は「手書き」「確定申告書等作成コーナー」「確定申告ソフト」の3つです。それぞれのメリットや注意点について解説します。
手書き
確定申告書は、税務署や市区町村の窓口のほか、税務署に連絡することで郵送受け取りも可能です。手書きで帳簿をつけ、手書きで申告書に記入する方法であれば、インターネットやパソコン、スマホに苦手意識があっても、作成可能です。また、費用もかかりません。
しかし、手書きは計算や記載のミス、記入漏れ、転記ミスなどをしてしまうことも考えられます。手書きで作成する場合は、十分に確認してから提出しましょう。
確定申告書等作成コーナー
国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、インターネット接続環境があれば、自宅から誰でも無料で利用できます。2019年よりスマホにも対応し、さらに便利になりました。案内ガイドに従って入力すると、自動的に確定申告書が完成します。
ただ、帳簿の作成や控除額の計算は、確定申告書等作成コーナーでは対応していません。あらかじめ計算する必要があります。
※参考 国税庁「確定申告書等作成コーナー」
確定申告ソフト
会計ソフトを使用することで、簿記の知識がない方も、簡単に帳簿作成ができます。基本的に案内に従って確定申告書類ができあがるため便利です。チャットやメール、電話などによるサポートも充実しており、わからない点があればすぐに質問できます。
一般的に、会計ソフトは有料です。買い切りタイプとサブスクリプションタイプがあるため、自分に合った方法を選択しましょう。
| 添付書類とともに提出する
確定申告書類の提出方法は、主に次の3つです。メリット・デメリットを紹介します。

税金の納付は、税務署または金融機関窓口による現金給付のほか、e-Taxでのダイレクト給付、インターネットバンキング、クレジットカード、コンビニ、スマホアプリなどがあります。
また、還付の場合は、確定申告時に記載した銀行口座情報に基づき、還付金が振り込まれます。ゆうちょ銀行の各店舗または窓口をあらかじめ指定することで、窓口受け取りも可能です。
確定申告をしなかった場合のリスク

確定申告を行わなければならないにも関わらず、面倒だと手続きをしなかった場合、罰金などのリスクが発生します。
確定申告をしなかった場合のデメリットについて、わかりやすく解説します。
| 罰金が科される
確定申告の対象者であるにも関わらず、正当な理由なく期限内に申告しなかった場合、本来納めなければいけない税金に加え、無申告加算税、延滞税などが課されるケースがあります。
無申告加算税は、納税額50万円までは15%、50万円超の場合は20%です。ただし、申告期限から1ヵ月以内に申告した場合や、期限内申告の意思があったと認められた場合は、無申告加算税は課されません。
また、延滞税は、本来の期限までに税金を納めなかった場合に課せられます。
延滞税の計算式は次の通りです。
- 納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合×法定納期限の翌日から完納日または2ヵ月を経過するまでの日数÷365日
- 納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合×2ヵ月を経過する日の翌日から完納日までの日数÷365日
※参考:国税庁|延滞税の計算方法
1と2の金額を足し、100円未満の端数を切り捨てた分が延滞税の額です。
| 税金を払いすぎてしまう
確定申告の義務がない方の場合、ペナルティは発生しません。しかし、給与から天引きされる源泉徴収税額は正確ではないため、払い過ぎた税金を取り戻すためには年末調整または確定申告が必要です。
確定申告を行わなければ、納め過ぎた所得税を取り戻す権利の放棄とみなされます。税務署から改めて連絡が来るわけではない点に注意が必要です。ただ、確定申告をし忘れていて過去の還付金を取り戻したい場合、5年以内であれば還付申告ができます。
派遣社員の確定申告に関するよくある疑問

派遣社員が初めて確定申告をしようとした場合、よくわからないと戸惑う方もいるでしょう。
ここでは、派遣社員の確定申告に関する疑問からいくつかピックアップし、わかりやすく解説します。
| 年収103万円以下でも必要?
年収103万円以下の場合、所得税を納める必要がありません。これは派遣社員も同じです。ただし、給与収入以外に副業などで得ている所得が20万円を超えている場合は、年収が103万円以下であっても確定申告が必要です。
【例】
- ・派遣の給与収入(年収)95万円→確定申告が不要
- ・派遣の給与収入(年収)60万円+副業の収入25万円=年収95万円→確定申告が必要
| 派遣会社を掛け持ちしている場合はどうすればいい?
2社以上の派遣会社を掛け持ちしている場合、年末調整を行えるのは、給料のもっとも多い1社のみです。さらにそのほかの派遣会社から源泉徴収票が発行されるのは、早くても年が明けてからです。
つまり、年末調整には間に合いません。そのため、自分で確定申告を行う必要があります。
| 派遣社員の確定申告書は何色?
確定申告には、青色と白色がありますが、派遣社員だから何色といった決まりはありません。派遣やアルバイト・パートなどの給与所得以外に、事業所得や不動産所得がある場合は、事前に税務署に青色申告を申請しておくことで、青色申告の対象になります。
青色申告と白色申告では、帳簿の付け方や控除額などルールが異なるため、自分の副業の内容と合わせて選ぶことをおすすめします。
派遣社員で確定申告が必要なケースを把握しておこう

派遣社員も、20万円超の副収入がある場合や医療費控除、住宅ローン控除の利用を検討している場合は、確定申告が必要です。確定申告をしなければ、ペナルティが課されたり、必要以上の納税をして損をしたりする可能性もあります。派遣スタッフとして働く場合、派遣会社が源泉徴収をしてくれますが、2社以上で勤務する場合は必ず自分で確定申告を行いましょう。
今、派遣の仕事を探している方、掛け持ちの仕事を探している方は、ワポティがおすすめです。ワポティ専任のコーディネーターが、あなたの就職活動、転職活動を徹底サポートします。自分のライフスタイルや希望に合った仕事を探している方は、お気軽にご登録ください。
ワポティの登録はこちら
あなたにピッタリなお仕事探しを応援します!